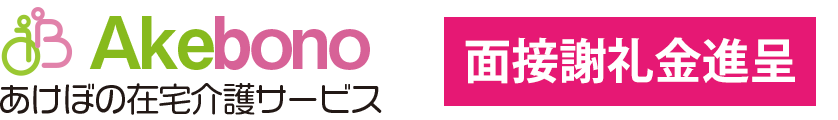判断能力の低下などにより、契約やお金の管理がむずかしくなった方を、法律に基づいて支援する制度のご案内です。ご本人の意思を尊重し、安心して暮らし続けるための手続きをサポートします。
成年後見制度とは
認知症・知的障がい・精神障がいなどの影響で、日常生活の重要な手続きが難しい場合に、家庭裁判所が選任した成年後見人等が、契約や財産管理、各種サービス利用の手続きを支援します。ご本人の意思を大切にし、できる限り自立した生活を尊重することが原則です。
このような不安に
- 銀行手続きや公共料金の支払い管理に自信がない
- 入退院や施設入所などの契約が難しい
- 訪問販売・詐欺などのトラブルが心配
- 申し立て方法や費用がわからない
※実際の支援範囲は家庭裁判所の審判内容によって異なります。詳細は専門職または家庭裁判所にご確認ください。
制度の種類(概略)
| 類型 | 対象のめやす | 主な支援 |
|---|---|---|
| 後見 | 判断能力がほとんど無い状態 | 財産管理や身上保護に関する幅広い代理権 等 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 重要な法律行為に同意権・取消権 等 |
| 補助 | 判断能力が不十分 | 特定の行為に限った同意権・代理権 等 |
ご相談から利用までの流れ
- ご相談:まずは当施設の相談窓口へ。状況とご希望をお聞きします。
- 制度の検討:必要性・類型の目安、申立て準備についてご説明します。
- 申立て:家庭裁判所へ申立て(書類作成・医師の診断書等)。
- 審判・選任:成年後見人等が選任されます。
- 支援開始:契約手続き、財産管理、サービス利用等を支援します。
申立てに必要な書類の例
- 申立書一式(家庭裁判所の書式)
- 医師の診断書
- 戸籍謄本・住民票 等
- 財産関係資料(通帳写し 等)
費用の目安
申立てに係る実費(収入印紙・郵便切手等)、鑑定が必要な場合の費用、選任後の報酬(家庭裁判所の審判による)など。具体額は事案により異なります。
よくあるご質問
誰が相談・申立てできますか?
ご本人、ご家族、市町村長等が関係法令に基づき申立て可能です。まずは相談窓口へご連絡ください。
後見人は家族以外でも大丈夫?
家族・親族のほか、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職、法人後見など、事案に応じて家庭裁判所が適切に選任します。
付き添いや家事支援も頼めますか?
成年後見は法的手続きや財産管理が中心です。付き添いや家事は介護保険・障害福祉サービス等の活用をご提案します。
お問い合わせ・相談窓口
権利擁護センターたなべ 成年後見 相談窓口
受付時間:平日8時30分~17時15分
市民総合センター2階(社会福祉法人 田辺市社会福祉協議会内)
電話:0739-24-8611
メール:anshin@tanabeshi-syakyo.jp
※地域包括支援センター、障がい者相談支援機関、家庭裁判所へのご相談も可能です。状況に応じてご案内します。
プライバシーと権利擁護
ご相談内容や個人情報は、関連法令と当施設の個人情報保護方針に基づき適切に取り扱います。ご本人の意思決定を大切にし、最適な支援方法を一緒に検討します。
最終更新日: